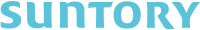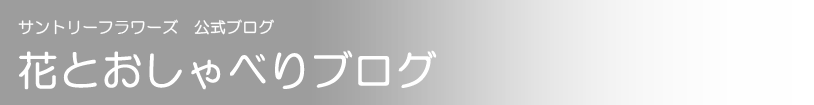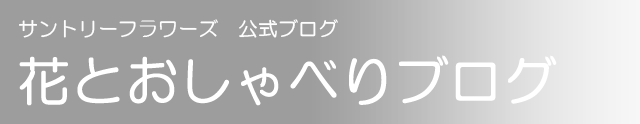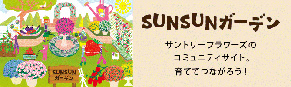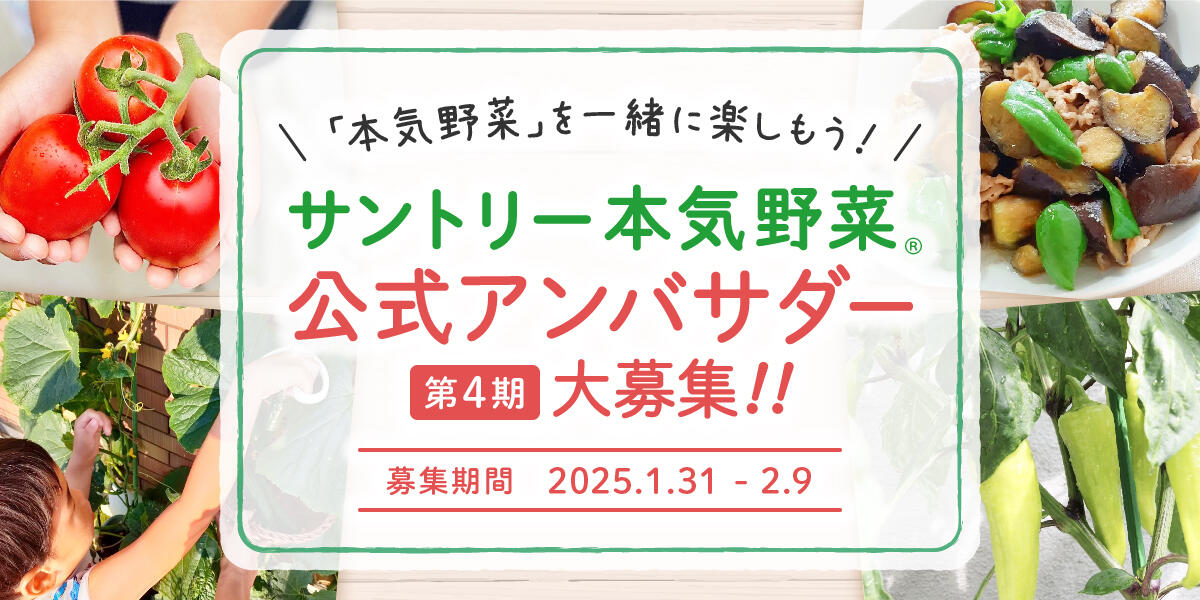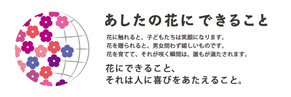どうする?収穫後の畑~秋に向けた土のリセット術~
2025年08月19日

夏の陽ざしを浴びて育った野菜たちも、だんだんと収穫の季節を終えつつありますね。
夏野菜の収穫が終わった後は、畑やプランターの整理と秋の栽培準備が必要です。病害虫の予防や土壌改良を行うことで、次の季節の野菜づくりがスムーズになりますよ。それでは、夏野菜の後片付けについて解説します!
片付けはいつやるの?

※秋まで収穫が続く、ナス・ピーマン類は10月中旬を目安に片付けて秋野菜に移行しましょう。
夏野菜の後片付け方法
① 枯れた野菜の撤去 収穫が終わった野菜は根ごと抜く → 病気や害虫の温床になるため、放置せずに早めに処理します。 病気があった株は焼却、またはゴミとして処分 → 堆肥にすると病原菌が残る可能性があるので注意してください。
② 支柱・ネットの片付け 泥や病原菌を洗い落とす → 次回も使えるように、しっかり洗って乾燥させて保管しましょう。
③ 土の掃除 ふるいにかけ前作の枯れ葉や根、種子を取り除く → 畝間やプランターの周りの雑草も忘れずに行います。雑草も病害虫の隠れ場所になるので、徹底的に除去しましょう。

土のリセット
土壌のバランスを整えよう
片付け後は十分に熟成したや石灰や堆肥、肥料を投入して土を耕します。
① 天地返し(てんちがえし)
目的:土の中の病原菌・害虫・雑草の種を地表に出して、太陽光や乾燥で死滅させる。
方法:スコップや鍬で深さ20〜30cmほど掘り返す。 → 表層の土と下層の土を入れ替えるように混ぜる。晴れた日が続くタイミングで行うと効果的です。
ポイント: 雨の前後は避ける(湿った土は重く、作業が大変)。 → 作業後は数日間、土を乾かしておくと良いです。
② 有機石灰の散布
目的:野菜の栽培で酸性に傾いた土壌の酸度を調整し、カルシウムを主としたミネラル分を補給する。
ポイント:有機石灰をまいた後はよく耕して1~2週間程度土になじませる。※石灰と堆肥・肥料は同時に混ぜない(化学反応でアンモニアが発生することがある)。また、予め土壌の酸度を測定し、必要に応じて加えてください。

③ 堆肥や腐葉土の投入
目的:土の保水性・通気性・栄養バランスを改善し、微生物の活動を活性化する。
使い方:堆肥(牛糞・鶏糞・植物性など)を1㎡あたり2〜3kg程度、腐葉土は1㎡あたり1〜2kg程度を土に均等に広げて、よく混ぜ込みます。
ポイント:完熟堆肥を使う(未熟なものは根を傷める可能性あり)。 腐葉土は通気性を高めるので、粘土質の土に特に効果的。
④ 1〜2週間の休ませ期間
目的:土壌改良材がなじみ、微生物が安定する時間を確保する。
方法:土を整えた後は、1〜2週間ほど植え付けを控える。 → この間に雑草が出たら除去しておくと、秋野菜の育成がスムーズです。
秋野菜を植えない場合の対応方法
「寒晒し(かんざらし)」
秋野菜を植えない場合は、冬場に行う土づくりの作業として「寒晒し(かんざらし)」がおすすめです。
① 作業時期を選ぶ:12月〜2月の寒い時期が最適です。 霜が降りる地域では、寒さによる凍結・解凍の効果が高まります。
② 土を掘り返す(天地返し):スコップや鍬で深さ20〜30cmほど土を粗く掘り返す。 表面の土と下層の土を入れ替えるように混ぜる。 この作業で、土中の病原菌・害虫の卵・雑草の種を地表に出します。
③ 土をそのままさらしておく:掘り返した土は畝を作らず、平らに広げて放置。 雨・霜・風・雪などの自然の力で、土が浄化・改良されます。 マルチやシートはかけずに、むき出しのままにしておくのがポイント。

夏野菜の収穫を終えた畑やプランターは、少しの手間をかけることで、次の季節に向けてぐっと育てやすい土に生まれ変わります。秋野菜を植えない場合でも、寒晒しなど自然の力を活かした土づくりをしておけば、春にはまた元気な野菜たちが育ってくれるはずです。季節の移ろいに合わせて、畑もひと休み。そんな時間も、家庭菜園の楽しみのひとつですね。